研究室からのお知らせ
【令和6年度】
・卒業生の早坂、M1の濵嶋、4年生の吉田、D1の森、D2の加藤、D3の鈴木、M2の釣上らが中心になって、生物資源学科の兒島先生と共同で行った研究内容が、Applied and Environmental Microbiology誌に掲載されました。(1月)
・セルラーゼ研究会(那覇)にてD3の鈴木と4年生の塚田が発表しました。また、塚田がポスター発表賞を受賞しました。(12月)
・日本応用糖質科学会中部支部会(静岡)にてD3の鈴木が発表しました。(12月)
・愛知県農学系4機関による研究交流会(名古屋)にてM1の川嶋、西垣、濵嶋が発表しました。(12月)
・D2の加藤が中心になって、産総研の三浦先生と共同で執筆した総説が、Applied Microbiology and Biotechnology 誌に掲載されました。(11月)
・第23回糸状菌分子生物学カンファレンス(沖縄)にてD2の加藤、D1の森、M1の鈴木、原崎が発表しました。(11月)
・第16回日本醸造学会若手シンポジウム(東京)にてM2の沼波が発表しました。(10月)
・日本生物工学会2024年度大会(東京)にてD2の加藤、M1の濵嶋が発表しました。また、加藤が学生最優秀発表賞を受賞しました。(9月)
・生物工学若手研究者の集い2024(北海道)にてD2の加藤、M1の川嶋、西垣、濵嶋が発表しました。(6月)
【令和5年度】
・ISPlasma 2024(名古屋)にてD2の鈴木とD1の加藤が発表しました。(3月)
・D1の加藤、卒業生の高橋らが中心になって、北海道大学大学院農学研究院の高須賀先生の研究グループと共同で行った研究内容が、Applied and Environmental Microbiology誌に掲載されました。(12月)
・日本食品科学工学会中部支部会(名古屋)にてM1の酒井が発表し、優秀発表賞を受賞しました。(12月)
・愛知県農学系4機関による研究交流会(名古屋)にてM2の鈴木、亀山、M1の釣上、沼波が発表しました。(12月)
・第22回糸状菌分子生物学カンファレンス(徳島)にてD2の鈴木、D1の加藤、M2の三浦、M1の釣上が発表しました。また、釣上が学生優秀発表賞を受賞しました。(11月)
・産総研の三浦先生が中心になり、M1の釣上、D1の加藤と共同で行った研究内容が、Applied Microbiology and Biotechnology 誌に掲載されました。(10月)
・日本生物工学会2023年度大会(名古屋)にてM1の岩井、沼波、中村、4年生の濵嶋が発表しました。(9月)
・D1の加藤が生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を受賞しました。(9月)
・生物工学若手研究者の集い夏のセミナー2023にてM1の釣上、D1の加藤が発表しました。また、釣上が専門分野プレゼン賞を受賞しました。(6月)
【令和4年度】
・日本農芸化学会2023年度大会(オンライン)にてM1の亀山、早坂、3年生の川嶋が発表しました。(3月)
・D1の鈴木、卒業生の森らが中心になって行った研究内容が、Journal of Bioscience and Bioengineering 誌に掲載されました。(1月)
・日本応用糖質科学会中部支部会(岐阜)にてM2の野村が発表しました。(12月)
・愛知県農学系4機関による研究交流会(オンライン)にてM1の亀山、半田、4年生の釣上が発表しました。(12月)
・第21回糸状菌分子生物学カンファレンス(オンライン)にてM2の加藤とM1の亀山が発表しました。また、加藤が学生優秀発表賞を受賞しました。(11月)
・日本農芸化学会中部支部会(名古屋)にてM1の早坂が発表しました。(10月)
・日本生物工学会2022年度大会(オンライン)にてM1の早坂、古澤T、三浦が発表しました。(10月)
・D1の鈴木、卒業生の森島、M1の半田らが中心になって行った研究内容が、Applied Biochemistry and Biotechnology 誌に掲載されました。(8月)
・M2の加藤、M1の古澤T、卒業生の森、D1の鈴木らが中心になって行った研究内容が、Applied Microbiology and Biotechnology 誌に掲載されました。(5月)
・M2の加藤、卒業生の酒井、伊藤らが中心になって行った研究内容が、ACS Omega 誌に掲載されました。(4月)
【令和3年度】
・日本農芸化学会2022年度大会(オンライン)にてM1の野村、4年生の早坂が発表しました。(3月)
・ISPlasma 2022(オンライン)にてM1の加藤が発表し、Best Presentation Award を受賞しました。(3月)
・日本応用糖質科学会中部支部会(オンライン)にてM2の森島が発表しました。(12月)
・愛知県農学系4機関による研究交流会(オンライン)にてM2の森、髙橋、M1の榊原、鈴木、野村が発表しました。(12月)
・M1の野村、卒業生の都築らが中心になって行った研究内容が、Food Chemistry: Molecular Sciences 誌に掲載されました。(11月)
・第20回糸状菌分子生物学カンファレンス(オンライン)にてM2の森とM1の加藤、野村が発表しました。また、野村が学生優秀発表賞を受賞しました。(11月)
・日本生物工学会2021年度大会(オンライン)にて研究生の鈴木、M2の森、髙橋、M1の小林、野村、4年生の亀山が発表しました。(10月)
最近の主な論文・著書
Hayasaka M, Hamajima L, Yoshida Y, Mori R, Kato H, Suzuki H, Tsurigami R, Kojima T, Kato M, Shimizu M.
Phenanthrene degradation by a flavoprotein monooxygenase from Phanerodontia chrysosporium. Appl. Environ. Microbiol., 90, aem.01574-24, 2025
Kato H, Miura D, Kato M, Shimizu M.
Metabolic mechanism of lignin-derived aromatics in white-rot fungi. Appl. Microbiol. Biotechnol., 108, 532, 2024
Kato H, Takahashi Y, Suzuki H, Ohashi K, Kawashima R, Nakamura K, Hori C, Takasuka TE, Kato M, Shimizu M.
Identification and characterization of methoxy- and dimethoxyhydroquinone 1,2-dioxygenase from Phanerochaete chrysosporium. Appl. Environ. Microbiol., 89, aem.01753-23, 2024
Miura D, Tsurigami R, Kato H, Wariishi H, Shimizu M.
Pathway crosstalk between the central metabolic and heme biosynthetic pathways in Phanerochaete chrysosporium. Appl. Microbiol. Biotechnol., 108, 37, 2024
Suzuki H, Mori R, Kato, M, Shimizu M.
Biochemical characterization of hydroquinone hydroxylase from Phanerochaete chrysosporium. J. Biosci. Bioeng., 135, 17-24, 2023
Suzuki H, Morishima T, Handa A, Tsukagoshi T, Kato, M, Shimizu M.
Biochemical characterization of a pectate lyase AnPL9 from Aspergillus nidulans. Appl. Biochem. Biotechnol., 194, 5627-5643, 2022
Kato H, Furusawa TT, Mori R, Suzuki H, Kato M, Shimizu M.
Characterization of two 1,2,4-trihydroxybenzene 1,2-dioxygenases from Phanerochaete chrysosporium. Appl. Microbiol. Biotechnol., 106, 4499-4509, 2022
Kato H, Sakai K, Itoh S, Iwata N, Ito M, Hori M, Kato M, Shimizu M.
Enhanced bioremediation of 4-chlorophenol by electrically neutral reactive species generated from non-thermal atmospheric pressure plasma. ACS Omega, 7, 16197-16203, 2022
Nomura R, Tsuzuki S, Kojima T, Nagasawa M, Sato Y, Uefune M, Baba Y, Hayashi T, Nakano H, Kato M, Shimizu M.
Administration of Aspergillus oryzae suppresses DSS-induced colitis. Food Chemistry: Molecular Sciences, 4, 100063, 2022
Yamashita M, Tsujikami M, Murata S, Kobayashi T, Shimizu M, Kato M.
Artificial AmyR::XlnR transcription factor induces α-amylase production in response to non-edible xylan-containing hemicellulosic biomass. Enzyme Microb. Technol., 145,109762, 2021
Sakai K, Yamaguchi A, Tsutsumi S, Kawai Y, Tsuzuki S, Suzuki H, Jindou S, Suzuki Y, Kajimura H, Kato M, Shimizu M.
Characterization of FsXEG12A from the cellulose-degrading ectosymbiotic fungus Fusarium spp. strain EI cultured by the ambrosia beetle. AMB Express, 10, 96, 2020
Ito S, Sakai K, Gamaleev V, Ito M, Hori M, Kato M, Shimizu M.
Oxygen radical based on non-thermal atmospheric pressure plasma alleviates lignin-derived phenolic toxicity in yeast. Biotechnol. Biofuels, 13, 18, 2020
Tsutsumi S, Mochizuki M, Sakai K, Ieda A, Ohara R, Mitsui S, Ito A, Hirano T, Shimizu M, Kato M.
Ability of Saccharomyces cerevisiae MC87-46 to assimilate isomaltose and its effects on sake taste. Scientific Reports, 9, 13908, 2019
Kamijo J, Sakai K, Suzuki H, Suzuki K, Kunitake E, Shimizu M, Kato M.
Identification and characterization of a thermostable pectate lyase from Aspergillus luchuensis var. saitoi. Food Chem., 276, 503-510, 2019
Sakai K, Matsuzaki F, Wise L, Sakai Y, Jindou S, Ichinose H, Takaya N, Kato M, Wariishi H, Shimizu M.
Biochemical characterization of CYP505D6, a self-sufficient cytochrome P450 from the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium. Appl. Environ. Microbiol., 84, e01091-18, 2018
Shimizu M.
NAD+/NADH homeostasis affects metabolic adaptation to hypoxia and secondary metabolite production in filamentous fungi. Biosci. Biotechnol. Biochem., 82, 216-224, 2018
Sakai K, Kimoto S, Shinzawa Y, Minezawa M, Suzuki K, Jindou S, Kato M, Shimizu M.
Characterization of pH-tolerant and thermostable GH 134 β-1,4-mannanase SsGH134 possessing carbohydrate binding module 10 from Streptomyces sp. NRRL B-24484. J. Biosci. Bioeng., 125, 287-294, 2018
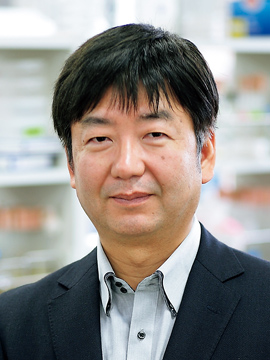 加藤雅士 教授
加藤雅士 教授 志水元亨 准教授
志水元亨 准教授










